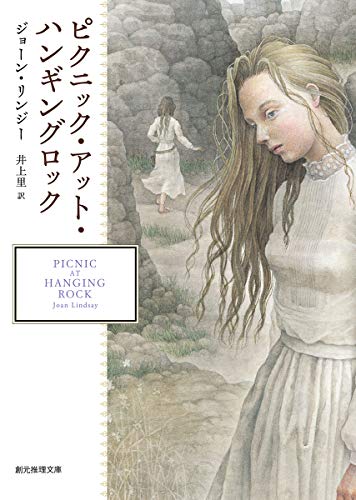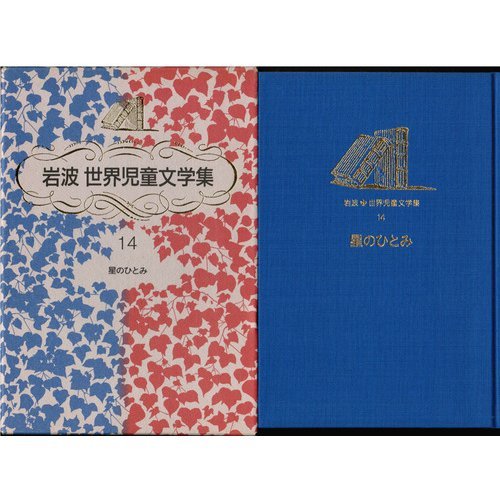数年前に公開して以来、ぼちぼちと更新を続けていた「季節の海外文学」リスト。どれも最初に公開したときは大体15〜20冊程度だったので、「いつかそれぞれ25冊まで増やして、全部で100冊になるといいな〜」と考えていたのだが、けっこうあっという間に100冊集まってしまった。ので、改めてまとめの記事を投稿します。
わたしは夏生まれだからか、そもそも「夏に読みたい小説」特集を見るのが大好き。日本文学だと怪談とか夏休みの物語とか、はたまた読書感想文のアイデア・ヒントとして、いくつもそういう特集がありますよね。海外文学でも、「夏」を感じさせる題名や装丁の作品はついつい購入してしまうので、それをブログ記事にしてみたのが始まり(そんなわけで「夏」リストだけは最初から完成していた)。
以下がとんでもない誤字脱字(いつもながら……)を修正したリストです。できるだけ日本語訳が出ているもので揃えたかったのだが、英語のみのものも(日本語に翻訳される確率は高いとは思う)。
みなさまのおすすめも、ぜひぜひ教えてください!
- 春の世界文学 25冊
- 夏の世界文学 25冊
- 夏そのもののような2冊
- タイトルに「夏」が入る6冊
- 夏が舞台の12冊
- 『太陽がいっぱい』パトリシア・ハイスミス(佐宗鈴夫訳)
- 『ある微笑』フランソワーズ・サガン(朝吹登水子訳)
- 『ベル・ジャー』シルヴィア・プラス(青柳裕美子訳)
- 『青い麦』コレット(河野万里子訳)
- 『夜はやさし』F・スコット・フィッツジェラルド(森慎一郎訳)
- 『グルブ消息不明』エドゥアルド・メンドサ(柳原孝敦訳)
- 『世界のすべての7月』ティム・オブライエン(村上春樹訳)
- 『異邦人』カミュ(窪田啓作訳)
- 『レクイエム』アントニオ・タブッキ(鈴木昭祐一訳)
- 『結婚式のメンバー』カーソン・マッカラーズ(村上春樹訳)
- 『ダロウェイ夫人』ヴァージニア・ウルフ(土屋政雄訳)
- 『ヘビトンボの季節に自殺した五人姉妹』ジェフリー・ユージェニデス(佐々田雅子訳)
- 子ども時代の夏の日を思い出す1冊
- ちょっと怖い3冊
- 夏休みにこそ読みたい1冊
- 秋の世界文学 25冊
- 冬に読む世界文学 25冊
春の世界文学 25冊
タイトルに「春」が入る6冊
『春にして君を離れ』アガサ・クリスティー(中村妙子訳)
アガサ・クリスティーがメアリ・ウェストマコット名義で執筆した小説。
イギリスの専業主婦として生活してきたジェーンが、娘家族の暮らすテヘランを訪れる。その一人旅における、ジェーンの心模様を繊細に描き出す。
ロマンス小説と紹介されることが多いが、どうだろうか。ある意味サスペンスだし、ミステリーでもある。
他の人の本当の気持ちを知ることは不可能だとしても、ここまで食い違ってしまうことはあるのだろうか? もしかして、自分が気付いていないだけで、自分も誰かにとってジェーンのような存在なのだろうか?
『春のめざめ』フランク・ヴェデキント(酒寄進一訳)
何度もミュージカル化されている物語。思春期に差し掛かった少年少女の性の目覚めと、それを恐れ抑圧しようとする大人たちを描く。
生き生きとした少年少女は、まさに春そのもの。出版された1891年当初には、さぞかし波紋を呼んだだろうと想像できる。
リア・ミシェル主演でミュージカル映画化される話が数年前にあったのだが、その後どうなったのだろう……。楽しみに待っているのですけれど。
『思春期病棟の少女たち』スザンナ・ケイセン(吉田利子訳)
青春期の持つ不安定な感じが、春にぴったりくる気がする作品。『17歳のカルテ』というタイトルで映画化。
麻薬中毒や精神疾患で入院するというのは、この小説が出版された当時(1993年)は今ほどよく聞く話ではなかった、はず。
映画では若かりし頃のアンジェリーナ・ジョリーが演じたリサという女の子がとにかくエキセントリック。女の子たちのキャラクターのおかげで、ともすれば暗くなりがちな物語がユーモラスに彩られている。
こちらも、洋書が非常に読みやすいので英語で読むのもおすすめ。
映画はこちら。
青春=人生の春。
『ミス・ブロウディの青春』ミュリエル・スパーク(岡照雄訳)
原題は『ミス・ブロウディの最良の時』というニュアンスなのだけれど、ブロウディ先生に「一流中の一流の女性」になるように教育された少女たちの思春期を描いた小説。
登場人物に対する風刺がなんともイギリス的。
『わが青春の輝き』マイルズ・フランクリン(井上章子訳)
子供の頃読んで、感想が言葉にならないほど感銘を受けた本。
オーストラリア人作家の自伝的小説。主人公の少女シビルは貧しい両親のもとに生まれるが、10代になると裕福な祖母に引き取られ、新しい生活を始めることになる。傲慢な一面もあるものの素直でまっすぐな彼女は、ハリーという青年と出会い恋に落ちる。甘い生活、その後やってくる何年もの別離、果てしない喧嘩の末に、夢(作家になりたい)を追いかけたいから結婚はできないとハリーに告げるシビルだが……。
『風と共に去りぬ』のスカーレットに似た、熱い魂を持つ少女の物語。
Spring / アリ・スミス

Spring: 'A dazzling hymn to hope’ Observer (Seasonal Quartet)
- 作者:Smith, Ali
- 発売日: 2019/03/28
- メディア: ハードカバー
アリ・スミスによるSeasonal Quartetの3冊目は、春。といっても物語が動くのは秋だったりして、決して春らしい春を描いた小説ではない。
それでも、春を待つ人の言葉や、春の終わりを嘆く人の態度が印象的で、改めてこの季節の素晴らしさを噛み締める。
新しい人生が始まる3冊
『フラニーとゾーイー』サリンジャー(野崎孝訳)
感じ方・受け取り方は変わると思うので10代、20代、30代と読み返したい1冊。
社会制度や環境の変化に混乱しているフラニー(妹)とゾーイー(兄)の会話。フラニーの心に染み込んでゆく、ゾーイーの言葉の数々。言うことすべてにセンスがある。
「もしも制度相手に戦争しようというんなら、聡明な女の子らしい銃の撃ち方をしなくっちゃ、だって敵はそっちなんだろう」
村上春樹による翻訳もあり。こちらの方が分かりやすいかもしれない。
『オレンジだけが果物じゃない』ジャネット・ウィンターソン(岸本佐知子訳)
青春を描いた作品、それも著者の自伝的小説にしてデビュー作である。
ウィットに富んでいて、時にほろ苦い。熱心なキリスト教徒である母に抑圧されて育ったジャネットのキリスト教への考え方の変化、そして家族や宗教的に決して許されない相手との初恋と自身のアイデンティティについて。
若い女の子がもがき苦しみながら、自分の信念を確立していく話。
『すばらしい新世界』オルダス・ハクスリー(水戸部功・大森望訳)
ああ、不思議なこと! ここにはなんて素敵な人達がいるんでしょう。人間はなんて美しいんでしょう。素晴らしい新世界。こんな人々が住んでいるんですもの!
(『テンペスト』シェイクスピア より)
1930年代に出版されディストピア文学の源となったこの作品も、帯で伊坂幸太郎さんが語っている通り「心地良い浮遊感があって」春に読むと「うっかり楽しい気持ちに」なってしまいそう。
新生活に絶望してしまいそうな時に読むのも……いいかも。
桜をモチーフにした2冊
『桜の園』 チェーホフ(神西清訳)
19世紀ロシアの没落貴族の物語だが、 チェーホフがそこに描くのは人間の普遍性、ユーモア、皮肉、悲劇とコメディである。だからこそ時を超えて、繰り返し世界中の人に読まれているのだろう。
太宰治の『斜陽』、吉田秋生の『櫻の園』など、『桜の園』に影響を受けて生まれた名作が多いことにも注目したい。
チェーホフの『桜の園』を毎年上演する女子校演劇部の生徒たちの物語。
『蝶の舌』マヌエル・リバス(野谷文昭・熊倉靖子訳)
マヌエル・リバスはガリシア語で執筆するスペイン人作家。スペインでは色々と出版されているが、日本語に翻訳されたのはこれ1冊のみ。とにかくどの短編も素晴らしい! ので、今では入手しにくいのが残念。
春が来るといつも思い出すのが、「愛よ、僕にどうしろと?(¿Qué me quieres, amor?)」という作品。
僕は夏が来て最初に摘むサクランボの夢を見る。
という冒頭と、サクランボを口移しに食べ、軸を舌で結んでしまう可憐な恋人の描写が印象的(ちなみにスペインではサクランボが実るのは5月頃。バルセロナではサクランボ祭りも催される)。
緑を感じさせる2冊
『大いなる遺産』チャールズ・ディケンズ(佐々木徹訳)
これはもう完全に映画の影響である。
アルフォンソ・キュアロン監督の『大いなる遺産』が素晴らしくて! キュアロン監督は緑が大好きなようで、どの映画を見てもとにかく緑の使い方が美しいのだが、 『大いなる遺産』では登場人物が緑を着て登場する。グウィネス・パルトロー、瞳と衣裳の色が同じ。きれい……。
様々なトーンの緑が、まるで春そのもの。
ディケンズの原作も、もちろん負けず劣らず面白い。
『緑の髪のパオリーノ』ジャンニ・ロダーリ(内田洋子訳)
『パパの電話を待ちながら』に次ぐ、内田洋子さん訳のジャンニ・ロダーリ。短いお話ばかりなのだけれど、どれもユーモアたっぷりで心地いい余韻が残る。
童話風の話でも、決して「道徳的」ではないのがいい。子どもに対して「こうしないと、ああなるんだぞ!」ではなくて、「こうだったらいいよね、楽しいよね」というおおらかな姿勢が本当に好き。
そしてやっぱり猫の話がいい! ローマの人々が関西弁を使っているのもいい! すごく合ってる!
春が舞台の4冊
『とうもろこしの乙女、あるいは七つの悪夢』ジョイス・キャロル・オーツ(栩木玲子訳)
オーツの、悪意にあふれた短編集。表題作「とうもろこしの乙女」は4月に起こった出来事について書かれている。
誰からも注目されないような地味で目立たない女の子グループが、金色に輝く髪を持つ知恵遅れの美しい少女を誘拐し、インディアンの儀式さながらに生贄にしようと企むという話。このような作品はアメリカという広大な国を舞台としてしか書けないのではないかという気がする。どことなく不安な気持ちが残る短編たちは、天気も気圧も不安定な春にぴったりかもしれない。
『魅せられて四月』 エリザベス・フォン・アーニム(北條元子訳)
絶版になっているのが残念だけど、映画化もされています。時代は第1次世界大戦後。花々が美しく印象的な4月のイタリア・ポルトフィーノを舞台に、イギリス人の四人の女性が登場する小説。人生に疲れ果てた中年の彼女たちがイタリアのとある古城を貸切にして、次々に生まれ変わっていく。
『わたしたちが光の速さで進めないなら(巡礼者たちはなぜ帰らない)』キム・チョヨプ(カン・パンファ / ユン・ジヨン訳)
冒頭の短編「巡礼者たちはなぜ帰らない」は、春になると村から旅立ち「始まりの地」に向かい、1年後の春に戻ってくる(あるいは戻ってこない)若者たちについての物語。巡礼者たちはどこへ向かい、何を見て帰ってくるのか? 巡礼前とは一体何が違っているのか?
宇宙をテーマにしたSFだけれど、「生まれる」ことの喜びや苦しみを感じさせる箇所もあり、遺伝子組み替えや整形が日常茶飯事となった現代社会を風刺しているようでもあり、母と子の絆やシスターフッドを描いた物語でもある。
『マンスフィールド短編集(幸福)』キャサリン・マンスフィールド(西崎憲訳)
「幸福」は、バーサという女性に訪れる、春のある1日を描いた物語。すばらしい空気、美しい花、春だからこそ感じられる生きているという喜び。幸福と不幸の入れ替わりも鮮やかで、もう1つの名作「ガーデン・パーティー」を彷彿とさせる(こちらも収録されている)。
初恋を描いた2冊
『朗読者』ベルンハルト・シュリンク(松永美穂訳)
とある男性が振り返る、自身の初恋。
「どうして、かつてはすばらしかったできごとが、そこに醜い真実が隠されていたというだけで、回想の中でもずたずたにされてしまうのだろう?」というミヒャエルの言葉が胸に刺さる。
本を読んであげるという甘く優しい行為がつなぐ関係は少年にとっては初恋だったが思わぬ形で長い間続くことになる。歴史(この場合は第2次世界大戦やナチス)が人生に与える影響と、人間の尊厳について考えさせられる。
「一読したときにはインパクトの強い事件ばかりが印象に残るが、二読目に初めて登場人物たちの感情の細やかさに目が開かれる」と訳者あとがきにあるが本当にその通り。
『エヴリデイ』デイヴィッド・レヴィサン(三辺律子訳)
これもある種の初恋を描いた小説。主人公のAは名前もなければ、性別も体も持たない。あるのは意識だけ。Aは毎日違う人物の体を借りて目覚めるのだ。
そんな彼がある日出会ったのがリアノン。彼女に恋をしてしまってからというもの、もう一度彼女に会うためにあらゆることを試してみる。しかし毎日違う体・違う性別で目の前に現れるAのことをリアノンは受け入れられるのか?
意識だけの存在・Aや、宿主となる少年少女たちの会話文がナチュラルで、訳も素晴らしい。
春にこそ読みたい長編1冊
『ミドルマーチ』ジョージ・エリオット(廣野由美子訳)
決してタイトルに「march」と入るからというわけではないのだけれど、春に読むのがぴったりだと感じる小説。
イギリスの地方都市ミドルマーチを舞台に、さまざまな登場人物の人生が交錯する。光文社古典新訳文庫はこの春(2021年)最終巻が出版され、ついに完結を迎えた。
春風のような4冊
『保健室のアン・ウニョン先生』チョン・セラン(斎藤真理子訳)
SFなのか、ロマンスなのか、ホラーなのか。色々なものがいっしょくたになった奇妙奇天烈な物語は、読んでいて本当に楽しい。霊能力の持ち主である保健室のアン・ウニョン先生が、高校に現れる邪悪な存在と戦う物語。ときどき現れる恋愛エピソードが春風のように心地いい。
映像化もされていて、Netflixで配信中。
『蜜のように甘く』イーディス・パールマン(古屋美登里訳)
稀代のストーリーテラー、イーディス・パールマン。すでに出版されていた『双眼鏡の眺め』も素晴らしいのだが、こちらの方が短いのと、「おとぎ話」をモチーフにしたパールマンらしい短編が並んでいるので、まずこちらを読むことをおすすめしたい。
もしかすると生まれたかもしれない恋、子どもをもって初めて知った喪失への恐れ、騎士のいるお城、ずっと心に残る父の胸の温かさと幸福感。
とてもシンプルなようでいて鮮やか、無駄な言葉がひとつもない物語を堪能できる贅沢な短編集。
『息吹』テッド・チャン(大森望訳)
SFのみならず文学の歴史に残るであろう名作。SFという舞台を用いて、人と人だけではなく人と機械、「なにか」と「なにか」の絆を描き続けているテッド・チャンの最新作。多作な作家ではないけれど、これだけであと何十年も楽しめること間違いなし。
『アラビアンナイト』、『東方見聞録』を思わせるような語り口の「商人と錬金術師の門」や、バーチャルな存在に対する愛情を描いた「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」など、春風のように新鮮で美しい作品ばかり。
『紙の動物園』ケン・リュウ(伊藤彰剛・古沢嘉通訳)
なんとなくもぞもぞと落ち着かない気分で(天気のせいかもしれない)、集中力散漫になりがちな春。では長編ではなくて短編を読もう。
もう有名になりすぎて、紹介するのも憚られるほどですが、ケン・リュウはやっぱりどれも面白い。SFだけれど少しおセンチなところも現代的でいい。
The Paper Menagerieという彼の短編集からとくに幻想的な短編が選ばれているのが、『紙の動物園』。
ダイヤモンドと鳩がモチーフの1冊
『ダイヤモンド広場』マルセー・ルドゥレダ(田澤耕訳)
けっして4月の誕生石がダイヤモンドだからというわけではないのだけれど。バルセロナで生まれ育った少女が恋を知り、大人になり、子どもを生んで、夫と死に別れ、老いていく。そんな一生が比較的淡々と語られているのに、あちらこちらでそれこそダイヤモンドのように、きらきらと光るエピソードが。
読み終わると、透明で冷たいダイヤモンドのかけらと、鳩の羽が心の底に残っているような気持ちになる。
夏の世界文学 25冊
夏そのもののような2冊
『観光』ラッタウット・ラープチャルーンサップ(古屋美登里訳)
タイ人作家による短編集。
観光が一大産業となっているタイで、貧しさを抱えながらも日々生活している人々を描き出している。盲目になりそうな母と旅する少年、観光地でアメリカ人の女の子に恋する青年、カンボジア難民の女の子。ジャスミンティーのように、どこか苦い後味の残る、味わい深いお話ばかり。
これはラープチャルーンサップのデビュー作なのだが、彼はこの作品以外何も書いていないのだ。素晴らしい物語ばかりで、もっと彼の小説を読みたいなと思うが、今はどうも消息不明だそうで!
マイペンライのタイ人らしいといえば、らしい。作家業からは足を洗ってしまったのだろうか。
『これもまた、過ぎゆく』ミレーナ・ブスケツ(井上知訳)
現代スペイン人作家ミレーナ・ブスケツによる、ある夏休みの物語。
裕福な家に育った40代女性。著名な母の陰に隠れるようにして生きてきた。そんな母が亡くなり喪失感に苦しむ彼女は、母が住んでいたカダケスで夏休みを過ごすことにする。元夫2人、息子2人、友人とその恋人たち、自身の愛人まで一緒に。
ハチャメチャな人間関係にまず目が行きますが、40代になっても母の影響下から抜け出せない&抜け出したくない複雑な娘心がこれでもかと描かれる。
サガンやウッディー・アレン、アルモドバルの映画を彷彿とさせる半自伝的小説。
タイトルに「夏」が入る6冊
『美しい夏』パヴェーゼ(河島英昭訳)
イタリア文学のネオレアリズモを代表する作家、パヴェーゼ。
あのころはいつもお祭りだった。家を出て通りを横切れば、もう夢中になれたし、何もかも美しくて、とくに夜にはそうだったから、死ぬほど疲れて帰ってきてもまだ何か起こらないかしらと願っていた、あるいはいっそのこといきなり夜が明けて人々がみな通りに出てこればよいのに、そしてそのまま歩きに歩きつづけて牧場まで、丘の向こうにまで、行ければよいのに。
という熱狂的に美しい文章から始まるこの小説は、16歳のジーニアと19歳のアメーリアという2人の少女の青春を描いている。
夏は何度も巡ってくるけれど、この夏とはもう二度と会えない……という郷愁を誘う物語。大人にこそ読んでいただきたい1冊。
『夏への扉』ロバート・A・ハインライン(福島正実訳)
夏になると必ず書店の目立つところに置かれているこのSF小説。1956年に発表された作品だが、ロングセラーである。
恋人に裏切られ、会社を乗っ取られた主人公は絶望し、愛猫ピートと2人で冷凍睡眠につく。そして未来で目覚めると、そこには……。タイムトリップの話なのだが、著者自身が1970年代や2000年代にタイムトリップしていたのでは? と疑ってしまうほど、現代的。スタートアップ企業の社員のやりとりはまるで今日のシリコンバレーを彷彿とさせるし、ルンバやCADのソフトウェアみたいな製品が出てくるし。IT畑の方、猫が大好きな方、ハッピーエンドのラブストーリーが読みたい方……にオススメ!
2021年には日本で映画も公開予定。
『真夏の航海』トルーマン・カポーティ(安西水丸訳)
みんながヴァカンスに旅立ち、誰もいなくなる真夏のニューヨーク。
1人取り残された17歳のお嬢様グレイディは、ブルックリン出身のユダヤ系の男の子クライドと出会い、両親には言えない恋を楽しむ。 夏のfling(遊びの恋)のつもりがだんだんとその関係は抜き差しならないものになっていき、2人の間に横たわる社会格差も無視できないものとなる……。
若き日のカポーティが書いた、非常に勢いのある物語。
『サマードレスの女たち』アーウィン・ショー(小笠原豊樹訳)
もう1冊、真夏のニューヨークを。こちらはアーウィン・ショーの短編集で、表題作はフィフス・アヴェニューでの夫婦の会話を描いたもの。「サマードレス」とはあるものの11月のお話で、実際に「サマードレス」を着た女たちが出てくるわけではない。サマードレスの女というのは、とある登場人物の頭の中だけに存在しているのですね。が、タイトルが夏らしいのでこちらのリストに入れちゃいます。
なんてことない(いや……なんてことあるかも)夫婦の会話と仲違いが描かれているのだが、最後のひねりがめちゃくちゃよくて、「違うだろ〜!!」と叫びたくなってしまう。のと、小笠原豊樹さんの訳がめちゃくちゃいい。全文書き写したくなるくらい。英語と日本語と1語ずつ見比べながら「そうきたか!」と膝を打つ。
『夏の夜の夢』シェイクスピア(松岡和子訳)
『夏の夜の夢』といえば『ガラスの仮面』を思い出してしまう……ガラかめでは、日比谷公園を彷彿とさせる大会堂で夏の夜、上演していましたね! マヤのパック!
妖精がいたずらして2組の男女カップルの思いが交錯し、大騒ぎに。喜劇なので非常に読みやすく、登場人物全てが印象的な名作。
シェイクスピア作品にしては珍しく女性のキャラクターが充実しており、魅力的なのもポイント。可憐な愛され女子ハーミアと、肉食系女子ヘレナ。
『ハローサマー、グッドバイ』マイクル・コーニイ(山岸真一訳)
特に日本で圧倒的な人気を誇るマイクル・コーニイのSF小説。とある星に住む男の子ドローヴが、避暑のためパラークシという港町を訪れるところから物語が始まる。宿屋の娘、ブラウンアイズとの恋愛模様を中心に描かれた青春ロマンス。非常に寒い星なので、swear words(くそ、ばか、みたいな汚い言葉)が「氷」に関係するものばかりというのが、面白い。
夏が舞台の12冊
『太陽がいっぱい』パトリシア・ハイスミス(佐宗鈴夫訳)
家柄もよく美しい娘ディッキーと、貧しくシャイなトム。イタリアの物憂げな小さい待ちモンジベロ(ハイスミスの創作)を中心に物語は展開される。トムの狡猾さに最初こそ嫌悪を覚えながらも、いつの間にか味方となり一緒にはらはらしているのだから不思議。この本に収められているのは、夏だからこそ起こった出来事かもしれない。
映画『リプリー』もキャストがぴったりで素晴らしかった。
ハイスミスはリプリーを主人公にした物語を他にも書いている。とにかくハイスミスの小説は読み尽くしたくなる。
『ある微笑』フランソワーズ・サガン(朝吹登水子訳)
サガンは夏の物語をたくさん書いていて、デビュー作『悲しみよこんにちは』も夏休みのお話なのだが、今日はこちらを。
『ある微笑』は彼女の2作目の小説で、『悲しみよこんにちは』に負けるとも劣らずな逸品。主人公のドミニックは大学生の女の子。同い年の素敵なボーイフレンドがいるにもかかわらず、彼の(既婚の)叔父を好きになってしまう。そんな一夏の物語。
これはズバリ、失恋した直後や恋愛で辛い思いをしている時におすすめである。日にち薬という言葉があるが、癒えない傷はないということを、恋愛の達人サガンは教えてくれる。
『ベル・ジャー』シルヴィア・プラス(青柳裕美子訳)
触れると壊れてしまいそうな、美しくも儚い1冊。タイトル(ベル・ジャー=ガラスの容器)通り。
ニューヨークの意外とむっとする気温を感じ、ティーンエイジャー独特の時間がいくらでもあるような雰囲気に浸れる。経験することすべてが初めてだという新鮮で静かな感動を、読書を通して味わえる。社会から疎外された若者の孤独感を描いているということで、『ライ麦畑でつかまえて』と比較されることの多い本。
『青い麦』コレット(河野万里子訳)
16歳のフィリップと15歳のヴァンカは幼馴染。親同士も仲が良く、毎年夏は一緒に海の別荘を訪れる。いつも仲良く遊んでおり、お互いに好意を抱いているフィリップとヴァンカだが、ちょうど思春期にさしかかった今年の夏。フィリップは妙にヴァンカを意識してしまい、今までと同じように接することができない。そんな時、カミーユ・ダルレー夫人という美貌の女性がフィリップの前に現れて……。
いつまでも子供のままではいられないという事実を突きつけられるような、決定的な一夏が描かれている。
ちなみに邦題は『青い麦』だが、フランス語の題はLe blé en herb(殻の中の麦、未熟な麦)。そして英訳はGreen Wheat。青と緑のperceptionの違いって面白いですね。日本語では未熟、若者=青ですものね。
コレットの他の作品では、『シェリ』もおすすめ。
『夜はやさし』F・スコット・フィッツジェラルド(森慎一郎訳)
フィッツジェラルドといえば東部出身だし、短編の「氷の宮殿」など、どちらかというと「冬」の描写が心に残る部類の作家。ただし、愛と憎しみでつながっていた妻ゼルダが南部出身だったように、「夏」や「暖かい場所」への憧れや手の届かないもどかしさが見え隠れするようにも感じる。
そんなフィッツジェラルドが夏休みを描いたらこうなる、という見本のような作品でもある。美しい南仏を舞台に、精神を病んでいく主人公や少しずつ関係性が壊れていく周りの人々。
『グルブ消息不明』エドゥアルド・メンドサ(柳原孝敦訳)
夏のバルセロナを練り歩いているかのような気持ちになる作品。主人公はひょんなことからバルセロナに不時着した宇宙人。とにかく面白い! どのページを見ても笑っちゃう。
『世界のすべての7月』ティム・オブライエン(村上春樹訳)
村上春樹の翻訳で一躍注目を集めたオブライエンの作品。
時は2000年7月7日。1969年に大学を卒業した男女が31年ぶりに同窓会で再会。ヴェトナム戦争を経験した者、カナダに亡命した者、青春時代の恋愛をひきずる者、重婚した者(!)、それぞれの人生の軌跡を振り返る。学生運動主導者、チアリーダー、ヒッピー、みんなそれぞれ人生の時間を重ね、同じように年を取っていく。
50歳というと肉体的には変化しても、精神的には20代とさほど変わらないのだろうなとしみじみ感じた。
『異邦人』カミュ(窪田啓作訳)
夏といえば『異邦人』は外せない1冊。
照りつける日差しを、ページの間から感じられるような小説である。主人公のムルソーは母の死を経験し、夏の暑さにやられ、 魔がさしたように犯罪を犯してしまう。
不条理だが、誰にでも起こりうる衝動を描いていて、人間とはこういうものなのかもしれないなあと思えてしまうのだ。
『レクイエム』アントニオ・タブッキ(鈴木昭祐一訳)
1932年7月30日。7月最後の日曜日に、物憂げなリスボンの街で死者たちに出会い、時間を過ごし、生前聞きたかったことをようやく聞いて、お別れをする「わたし」。
タイトルの通り優しい雰囲気のお話。うだるような暑さで、住人はみなバカンスに行ってしまいがらんとしたリスボンの町で過ごす真夏の1日が死者に会う日として選ばれるというのは、日本のお盆をも彷彿とさせる。
『結婚式のメンバー』カーソン・マッカラーズ(村上春樹訳)
こちらも、村上春樹訳によって再出版された物語。
「緑色をした、気の触れた夏」だった、という印象的な文章で始まる。アメリカの南部が舞台なので、熱く気だるい、街全体が昼寝しているような夏が美しく描写されている。
1940年代の12歳の女の子が過ごした一夏のお話。何が起こるというわけでもないが、子供から大人への第1歩、世界が変わってしまうような夏である。
『ダロウェイ夫人』ヴァージニア・ウルフ(土屋政雄訳)
ロンドン、6月のある朝。クラリッサ・ダロウェイは夜のパーティに備え、花を買いに出かけた。戦争は終わり、何気ない朝に感じる生きている喜びを噛みしめるクラリッサ。
意識の流れを代表する1冊ではあるものの、その初夏という季節の描写の美しさやクラリッサおよび周りの人々の生と死への観念が春ならでは。
『ヘビトンボの季節に自殺した五人姉妹』ジェフリー・ユージェニデス(佐々田雅子訳)
ソフィア・コッポラが映画化したことでも有名になった小説。学校でも憧れの的だった美人五人姉妹が、次々とその生を終えてしまう……。暑さに浮かされたような、多感な時期の女の子たちの行動が印象的。
ヘビトンボの季節=6月ということで、初夏に読みたい1冊。
子ども時代の夏の日を思い出す1冊
『ミネハハ』フランク・ヴェデキント(市川美日子訳)
森の中で世界から隔離され、暮らす少女たち。時折新しいメンバーが運び込まれては、成長した少女が出て行く。新陳代謝を繰り返しながら、少女たちは毎日歌い、踊る。晴れた日の木陰や、冷たい水の心地よさと、少女の美しさがまるで映像のよう。
大人になることへの不安を抱えていた思春期の夏の日を思い出させてくれる作品。何度か映画化もされている。
深緑野分さんの短編「オーブランの少女」も、この作品から着想を得たとあとがきに書いてあったような(映画の方だったかも?)。暑く、緑が濃い庭園の描写が印象的だった。深緑さんの作品はどれも海外文学や海外児童文学の影響を色濃く受けたように感じられて、その空気感がなんともいえず好き。
ちょっと怖い3冊
『ねじの回転』ヘンリー・ジェイムズ(小川高義訳)
なぜか、夏になると以前書いた『ねじの回転』のレビューが当ブログの「よく読まれている記事」に急浮上してくるので、こちらも入れてみる。確かに、この怪談めいたゴシック調の物語は夏の読書にぴったり。少し涼しくなるかも。
家庭教師の職を得た若い女性を待っていたのは、天使のようにかわいい兄妹。楽しい生活が始まるはずだった。ところが、しばらくすると彼女は家の中で幽霊を何度も目撃するようになり…。
『ラテンアメリカ怪談集』ボルヘス 他 鼓直 編
怪談つながりで、こちらも! 長らく絶版になっていた(よね?)この短編集だが、2017年復刊!
今は他では日本語で読むことができないような短編、たとえばルゴネスの「火の雨」やオカンポの「ポルフィリア・ベルナルの日記」も収録されているし、ボルヘスの「円環の廃墟」、パスの「波と暮らして」など多数の短編集に収録された名作も含まれている。ああ、贅沢。
『ピクニック・アット・ハンギングロック』ジョーン・リンジー(井上里訳)
2018年に日本語訳が出版されたオーストラリアの名作。時は2月(南半球の夏だ)、ハンギングロックまでピクニックに出かけた全寮制女子校の生徒ら3人と教師1人が行方不明になる。
どれほど暑くても木陰には清涼な空気が流れている様子や、ユーカリの白い木が作るオーストラリアならではの森の風景、昼寝する少女らの足元でうごめく昆虫など、風景描写の美しさが際立つ。
夏休みにこそ読みたい1冊
『失われた時を求めて』プルースト(高遠弘美訳、吉川一義訳)
夏休みにこそ読むべき小説といえば、やっぱりこれは外せないのでは。今いちばん新しい訳は高遠弘美さんの光文社古典新訳文庫と、吉川一義さんの岩波文庫。
秋の世界文学 25冊
タイトルに「秋」が入る3冊
まずは「秋」をタイトルに掲げた小説たち。
『族長の秋』ガブリエル・ガルシア=マルケス(鼓直訳)
ガルシア=マルケスの作品はどれもこれも、盛りを過ぎて終焉へと向かう人・一族・村が描かれているような気がするが、この小説も然り。
祖母から口頭で伝えられた民話や伝説が小説家になるきっかけだったという著者らしい文章で(改行がない)、とある独裁者の一生が語られる。インコの歌う歌が国中に広まったり、政敵を丸焼きにして宴の料理にしたり。魔術的な出来事が次々と起こる中で、100年間も権力を誇る大統領。段々と老いて弱々しくなっていく様に、人生において大切なものは何なのかと思いを巡らせてしまう。
くせになる味わい。
『秋』アリ・スミス(木原善彦訳)
2017年度のブッカー賞にノミネートされたアリ・スミスの作品。2016年、Brexitで揺れ動くイギリスを舞台に、101歳のダニエルと34歳(1984年生まれ、ディストピア界の申し子ともいえるかも)のエリザベスが過ごす秋、そして2人が一緒に過ごしてきたいくつかの秋についての物語。
本を読むことの大切さについても語られていて、まさに読書の秋にぴったり。
『夜愁』サラ・ウォーターズ(中村有希訳)
第2次世界大戦後のロンドンに暮らす複数の男女を描いた作品。タイトルも素敵で(原題はThe Nightwatchだった)、創元推理文庫の装丁も美しすぎる……。本当にこういう雰囲気なんです。物語が。
戦時に生まれた愛は、生と死が隣り合わせになっているような毎日を経て、穏やかな日常へと着地する。燃え上がるような太陽を体に感じたあとにやってくる静かな夜には1人で色々と考え事にふけってしまうように、平和になったはずの現代(1947年)にこそ浮かび上がってくる感情がある。
秋の月(9月、10月)が登場する3冊
『フォークナー短編集(乾いた9月)』フォークナー(龍口直太朗訳)
雨が最後に降ってから62日、からからに干からびたような9月。
とある白人女性が黒人男性にレイプされたという噂が町に流れる。その噂の真偽を確かめることもなく、町の男たちは加害者だとされた黒人男性をリンチするが……。
閉鎖的な南部の町の雰囲気、白人と黒人の間に横たわる壁、独身のまま年老いる女性の哀切、結婚していても孤独なカップル。それぞれの抱える痛みを描いた作品。
新潮文庫の『フォークナー短編集』に収録。
『10月はたそがれの国』レイ・ブラッドベリ(宇野利泰訳)
SF作家として有名なブラッドベリの初期の短編を集めた本。『10月は〜』という通り、夏休みが終わり、街からはサーカスやカーニバルが去り、海や岸辺からは人が去り、風が涼しくなる「秋」を背景に据えた作品ばかりで、この時期に読むには最適。
SFと呼べる作品は意外にも1つもなく、「死」をテーマにした奇妙な幻想小説ばかり。 背筋が凍るような話もあれば、シュガーコーティングされたホラーもある。
Sisters / デイジー・ジョンソン
語り手の少女、7月生まれのジュライ(July)は10か月しか違わない9月生まれの姉、セプテンバー(September)と双子のように育てられたが、2人の間には決して覆らない力関係が存在する。何をするにも一緒で、ジュライはセプテンバーがやれといったことをやり、やるなと言われたことはやらない。ダークな姉妹物語。
秋が舞台の2冊
続いては、秋に起こった出来事が描かれている小説。
『未亡人の一年』ジョン・アーヴィング(都甲幸治・中川千帆訳)
幼い頃、母マリアンが23歳も年下の少年エディと浮気している現場を目撃してしまうルース。 1958年の秋、マリアンは家族と愛人であるエディを残して失踪してしまう。そして月日は巡り、1990年の秋。売れっ子作家となったルースは、エディと再会する。エディも作家になっているのだが、こちらは全く売れていない。彼はいまだにマリアンを愛し続けていて……。
様々な人の立場から綴られる、愛と再生の物語。とにかく先が読めない展開で、最高のエンターテイメント。個人的に、ジョン・アーヴィングの著書の中で一番好き。
『泣きたい気分』アンナ・ガヴァルダ(飛幡祐規訳)
通りですれ違った男と恋に落ちたパリジェンヌ。彼はどこからどう見ても素敵、誘い方もユーモアのセンスもパーフェクト。ディナーデートに出かけ楽しい時間を過ごすが、思わぬ落とし穴が待っていた……。現代のパリに住む人々の日々の暮らしに潜む孤独を描いた短編集。
どれも少しほろ苦く、タイトル通り「泣きたい気分」にさせてくれる。
大恋愛を描いた4冊
秋といえば、恋愛に関しても思いを巡らせたい。
『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ(千野栄一訳)
冷戦下のプラハ。トマーシュは気ままな恋愛を楽しむ脳外科医だ。ある日、手術のため小さな町を訪れたトマーシュは、カフェのウェイトレス・テレザに出会う。テレザはトマーシュを追ってプラハに引っ越してくる。2人は同棲を始め、のちに結婚する。しかしトマーシュは複数の女性との恋愛をやめることはせず、特に結婚前から束縛しない関係を続けている画家のサビナとは長きにわたって関係を持った。傷ついたテレザは、それでもトマーシュのそばを離れられず……。
幾分哲学的な恋愛小説。カップル間の愛情(テレザは人生と表現するが)に関する価値感が違うと、これほど不幸なことになるというお手本のような話である。片方にとっては恋愛は楽しむものであり、代わりがいくらでもいるものである。もう一方にとっては、人生で1回しか起こらない、運命である。他人と分かり合うなんて、土台無理なことなのかもしれないと考えてしまう。
『昼が夜に負うもの』ヤスミナ・カドラ(藤本優子訳)
少しメロドラマっぽい展開がある本作品も、秋の読書にぴったり。
アルジェリア独立戦争の時代に生きた1人の男の物語。主人公ユネスはジョナスへと名を変え、持たざる者から持つ者へ変わり、「白人の中のアラブ人」から「アルジェリア人」へ変わる。自分自身でいるとは、なんと難しいことか。彼の人生はアイデンティティ模索の旅でもある。過去の後悔も取り返しのつかない失敗も、明日を作る糧となるとは簡単に言い切れないストーリー。でも最後のページは今までの葛藤や苦しみを補って余りある。
『ぼくの美しい人だから』 グレン・サヴァン(雨沢泰訳)
1980年代のアメリカ。27歳のマックスは広告代理店勤務のユダヤ系エリート独身貴族。美しい妻を数年前に亡くし、恋人も作らず仕事に精を出している。ある時、ハンバーガーショップの店員ノーラと出会う。ノーラは41歳独身、学歴もお金もない、ネイティブアメリカンの血が流れている女性である。ゆきずりの関係を1度だけ持った、はずだったのに2人は激しく惹かれあい何度も会うようになる。一見正反対の2人。マックスは、ノーラと付き合っていることを周囲にひた隠しにし、誰にも紹介すらしない。「こんな女」と一緒にいることを知られるのが恥ずかしいのだ。恋しているのは「こんな女」なのに……。
恋に落ちる相手は決して選べないという事実を思い知らされる1冊。新潮文庫の表紙(絶版?)は映画版の秋の公園でのワンシーン。
『日々の泡』ボリス・ヴィアン(曽根元吉訳)
『うたかたの日々』として出版されることも(訳としてはそれが正解)。
おぼっちゃまのコランは、ガールフレンドのクロエがかかった「肺に睡蓮が咲く」という奇病を治療するため、働きに出ることにするが何をしても上手くいかない。一方とある思想家(サルトルならぬパルトル)に入れあげている恋人シックを取り戻すため、思想家の暗殺を図る女の子アリーズ。
ピアノの音色で作るカクテルや、シナモンの香りのする雲。幻想的な描写や、やがて哀しき恋人たちの運命は、寒い冬が来る前に読みたい。
秋の夜長にぴったりな長編5冊
『充たされざる者』 カズオ・イシグロ(古賀林幸訳)
ヨーロッパの田舎町に仕事でやってきた音楽家・ライダー。ホテルに到着するやいなや、次々に町の人から不条理な依頼を受ける。ライダーは戸惑いながらも、断ることができないでいる。その中で彼は自身の人生や家族、友人について想いを馳せる。
カズオ・イシグロ得意の「信頼できない語り手」による、まるで夢の中を漂っているかのような物語。
秋はシリーズ物を読み始めるのにもぴったりな季節。
『ライラの冒険』フィリップ・プルマン(大久保寛訳)
ライラの冒険シリーズは、『黄金の羅針盤』、『神秘の短剣』、『琥珀の望遠鏡』の3冊(文庫ではそれぞれ上下巻分かれているので全6冊)。『指輪物語』、『ナルニア国ものがたり』につぐイギリス人作家による児童文学の名作。
児童文学とはいえ、この物語にはキリスト教を問うという大きな伏線があるので、本当に楽しめるのは大人かもしれない。
ニコール・キッドマン扮するコールター夫人が小説から抜け出てきたような雰囲気だっただけに、映画シリーズ化が頓挫してしまったのは残念。
『夜ごとのサーカス』アンジェラ・カーター(加藤光也訳)
サーカスの華・空中ブランコ乗りのフェヴァーズ。彼女の背中にはなんと、羽が生えている。 本物なのか、偽物なのか? ロンドン、サンクトペテルブルク、シベリアと舞台を変え、視点を変え、進む物語。
白粉、嬌声、香水やほこりでむせそうになるほど視覚的で音楽的な文章である。大人のおとぎ話という感じ。
『夜のみだらな鳥』ホセ・ドノソ(鼓直訳)
*水声社はAmazonでの販売を行っていないため、リンクはありません。お求めの場合は書店までぜひ。
サーカスといえば、こちらも。仮面をつけて別人になりすまし、仮装をして自分を偽る……。不妊や奇形児への不安からホセ・ドノソが生み出した、ファミリー・サーガの物語だが、サーカスを連想させる描写がいくつも現れる。
読んでいるうちにどこまでが夢でどこまでが現か分からなくなり、自分もアスコイティア家の呪いにかかったような気がしてくる。秋にこそ楽しみたい奇妙な傑作。
『千夜一夜物語』バートン版(古沢岩美・大場正史訳)
シャーリヤル王とシェーラザッドが過ごした夜も、秋の夜長といわれるような長い長い、心地いい夜だったに違いないという気がしてならない。
勇敢なシェーラザッドが、処女を毎日殺すという残虐な王のもとにくだり、王のために語る物語の数々。あれもこれも、『千夜一夜』がもとだったのだなあという話がたくさん出てくる。思いの外エロティックなのも特徴的。
謎に包まれた5冊
そして、ミステリーやサスペンス、謎から始まる物語も、秋に読むのがぴったりな気がする。
『またの名をグレイス』マーガレット・アトウッド(佐藤アヤ子訳)
1800年代のカナダで起きた事件を題材にした長編。16歳の美少女グレイス・マークスは、使用人とぐるになって雇い主キヌア氏および女中頭のナンシーを殺害した罪に問われる。
使用人は死罪となるものの、まだ少女で精神に混乱をきたしているとみられたグレイスはその後30年間も刑務所に留置されることとなる。グレイスは本当に殺害に関与していたのか?それとも……。ある精神科医にグレイスが語る、彼女から見た事件の真相とは?
Netflixでドラマ化された作品。
『大いなる眠り』レイモンド・チャンドラー(村上春樹訳)
フィリップ・マーロウという探偵を主人公にしたハードボイルド小説の1作目。ロサンゼルスで私立探偵となったマーロウが、とある事件の捜査依頼を受けるが……。
小説そのものがまるで映画のような、独特の風合いを持つ作品。マーロウは外見から中身まで、とにかくスタイリッシュでハードボイルド。そして美女と犯罪者がこれでもかというほど登場する。
『レイチェル』 ダフネ・デュモーリア(務台夏子訳)
デュ・モーリアの代表作『レベッカ』は、エマ・ワトソンのブッククラブOur Shared Shelfの2018年9-10月お題本にも選ばれているが、姉妹作と呼ばれる『レイチェル』も同じくらい面白い。
従兄弟のアンブローズはイタリアの血が流れる女性レイチェルと結婚後すぐに亡くなった。残された手紙から、主人公のフィリップはレイチェルが殺したのではないかと疑うようになる。かなり思わせぶりな描写が続くものの、謎は謎のまま終わるのがまた秋に読むのにぴったり。
舞台はイギリスのコーンウォール地方で、庭やお屋敷、レイチェルの美しい衣装や宝石の描写の素晴らしさには目を見張る。
『オペラ座の怪人』ガストン・ルルー(平岡敦訳)
最初に本を開いた時、音楽なしで、この「クズだらけのすったもんだ」をひたすら読むのは苦痛だろうな……という思いが頭をよぎったのは言うまでもない。
が、そこはさすがにフランスのミステリー界の礎を築いたと言われる作家ルルーだけある。エンターテイメント性に富んでおり、21世紀を生きる人間が読んでも&ストーリーを知っている者が読んでも楽しめる上に、訳者の平岡敦さんの力量もあり、とてもモダンで軽やか。
『贖罪』イアン・マキューアン(小山太一訳)
夏の暑い日、イギリスの片田舎で少女ブライオニーが仕事で家を離れている兄の帰省を待っているシーンから物語りは始まる。 夏草の匂いや涼しげな木陰と泉、触ると少しはひんやりしているであろうレンガの家や洗い立てのシーツの匂い、子供がお風呂に入ってはしゃぐ声。まだ幼いブライオニーが犯した、決して許されない罪とは……。
ジェイン・オースティンの引用から始まる作品。次第に話が哀しくなっていってもその冒頭を思い出すと、なんだか救いがある感じ。暗闇の中の光のような。
女ごころと秋の空な1冊
『女ごころ』W・サマセット・モーム(尾崎寔訳)
「女心と秋の空」という言葉があるので、この作品もリストに加えておこう。
モームの作品の中ではかなり短く、一番コミカルかもしれない中編小説。イタリアの山荘で暮らす美しき未亡人メアリーの、様々な男性との出会いとドタバタ劇が描かれている。町の情景や涼しい風が思い浮かぶようで楽しい1冊。幸せとは、比較や条件ではなく、結局心の満足度なのだなと思えるエンディング。モームって、どれを読んでも本当に面白い!
装丁からして《秋》な1冊
『昼の家、夜の家』オルガ・トカルチュク(小椋彩訳)
トカルチュクの作品はどれもなんとなく秋を感じる気がするが、こちらは日本語版の装丁に使用されている版画のタイトルもずばり、《秋》(ポーランドの画家、アリツィア・スラボニュ・ウルバニャックさんの作品で、日本のアートギャラリーに展示されていたそう。ギャラリーのオーナーさんのブログに記載があります)。
ポーランドとチェコの国境にある町、ノヴァ・ルダに住まう語り手によるとりとめのない話。昼と夜、家と外、男と女、意識と無意識など、対立しているはずのさまざまなイメージが、国の境にあるノヴァ・ルダそのもののように混ざり合い、1つに溶けていく。キノコや料理のレシピも多数登場し、食欲の秋としてもぴったり。
なんとなく秋を感じる1冊
『ゴドーを待ちながら』サミュエル・ベケット(安堂信也・高橋廉也訳)
特に季節に関して記述はないはず(何しろ舞台には木が1本だけ)だが、なぜか秋を感じ、秋に読み返したくなる作品。
アメリカでの初演では、最後まで残っていた客がテネシー・ウィリアムズとウィリアム・サローヤン(と役者の家族)だけだったという不条理演劇。一方フランスでは100回近く公演、一部は熱狂的なメディアもいたという。白水Uブックスでは、フランス版・イギリス版の違いも説明されているが、「え、そこ違ったら意味がまったく違うことにならない?」という箇所がいくつかあって興味深かった。意味なんて……そもそもないのかもしれないけど。初読の際はキリスト教のモチーフに目がいったのだが、最近は待つという行為に付随する色々な感情を味わうことにフォーカスしたいと思いながら読んでいる。
冬に読む世界文学 25冊
タイトルに「冬」が入る6冊
『冬の夜ひとりの旅人が』イタロ・カルヴィーノ(脇功訳)
「あなたはイタロ・カルヴィーノの新作『冬の夜ひとりの旅人が』を読み始めようとしている」という、出だしの文章が有名なメタフィクション。パラレルワールドがいくつも繰り広げられる。
読書の喜び、面白さをじっくり噛み締めることができる。
『冬の犬』アリステア・マクラウド(中野恵津子訳)

- 作者: アリステア・マクラウド,中野恵津子
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2004/01/30
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 4人 クリック: 56回
- この商品を含むブログ (68件) を見る
カナダ東部、ケープ・ブレトンが舞台の短編集。
氷に閉ざされ、1年のほとんどが厳しい寒さに覆われたような地域での人間と動物の物語。読んでいるだけで、髪の毛や涙まで凍ってしまいそう。
『マヨルカの冬』ジョルジュ・サンド(小坂裕子訳)
ジョルジュ・サンドが、ショパンと過ごしたマヨルカでの冬についてのエッセイ(ノンフィクション)。恋人の体調が悪く、マヨルカは思いの外寒い。終わりも見えている恋が物悲しい。
『冬の夢』スコット・F・フィッツジェラルド(村上春樹訳)
冬の寒さ厳しいアメリカ東部をモチーフにした短編集。
「氷の宮殿」は、暖かなアメリカ南部の娘が北部の青年と結婚し、北部を訪れる物語。あまりの環境や人間性の違いに彼女は驚き、カルチャーショックを受ける。そして青年の街で訪れた氷の宮殿では、あっと驚くような出来事が……。
『冬物語』シェイクスピア(松岡和子訳)
あまりに長すぎる冬=時の隔たりを経て訪れる、春を描いた物語。
Winter / アリ・スミス

Winter: from the Man Booker Prize-shortlisted author (Seasonal)
- 作者: Ali Smith
- 出版社/メーカー: Penguin
- 発売日: 2018/10/04
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログを見る
アリ・スミスが四季をテーマに、2015年以降のイギリスを舞台に執筆しているSeasonal Quartetの2作目。全てが死に絶える冬に、久しぶりに再会した家族と他人。クリスマスを一緒に過ごすことで、分かり合えないはずだった人との間に思わず絆が生まれる。
アリ・スミスらしくアートやシェイクスピアが大きなテーマになっていて楽しめる。
ロシア文学から2冊
『貧しき人びと』ドストエフスキー(木村浩訳)
厳しい寒さの中で生まれたロシア文学は、ぜひこの季節に味わいたい。
役人マカールと薄幸の美少女ワーレンカの間に交わされる書簡からは、貧困にあえぐ苦しみだけではなく、日常のかすかな喜びやお互いへの思いやりが感じられ、それはまるで晴れた冬の日に見つけた温かな光のよう。
短めなので、ドストエフスキー初心者の方にもおすすめである。彼の作家人生の初期に書かれたこともあり、社会文学ではあるものの情緒的で読みやすい。
『ドクトル・ジヴァゴ』ボリース・パステルナーク(工藤正廣訳)

- 作者: ボリースパステルナーク,イリーナザトゥロフスカヤ,工藤正廣
- 出版社/メーカー: 未知谷
- 発売日: 2013/03/14
- メディア: 単行本
- クリック: 7回
- この商品を含むブログ (6件) を見る
ノーベル賞作家ボリース・パステルナークによる長編小説。
ロマノフ王朝が終わりを告げ、ロシア革命が始まろうとしているモスクワ。主人公・ユーリ・ジヴァゴは学校を卒業し医師となったばかり。ある日、自身の婚約を発表するパーティーに若い娘が乱入し、客の1人を銃で撃ってしまう。娘の名前はラーラ。
2人は別々の相手と結婚するものの、人生の節目節目で巡り会い……革命や戦争の中でも死なない愛を描いた物語。
読み応えがあるので、冬じゅう楽しめること間違いなし。
カナダ文学から4冊
1年の半分は雪が降りしきる地方も多い国、カナダ。カナダ文学もぜひこの季節に。
『キャッツ・アイ』マーガレット・アトウッド(松田雅子・松田寿一・柴田千秋訳)
トロントで少女時代を過ごした女性アーティスト(画家)が、大人になってから仕事の関係でその地に戻り、子供の頃の友人に思いをはせるという物語。
いじめなどに見る少女の残酷性や、それが人生にどう影響するかということを考えさせられる。
トロントの冬、凍った池での出来事が印象的。
『犬の人生』マーク・ストランド(村上春樹訳)

- 作者: マークストランド,Mark Strand,村上春樹
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2001/11/01
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 12回
- この商品を含むブログ (22件) を見る
詩人、マーク・ストランドが書いた幾分詩的な短編集。ストランドはアメリカ人だが、カナダ生まれ。カナダの都市もいくつか登場する。
コーヒーとドーナツにとても合う、気がする。
カナダ人作家、再び。マンローも、アトウッドに並び有名な作家である。
『ディア・ライフ』アリス・マンロー(小竹由美子訳)
音も無く深々と雪が降り積もり、翌朝起きたら家の窓は一面銀世界になっていた……というような静かな驚きに満ちた短編集。静かに凍るトロントの道路も、美術館も、田舎の風景もなんということはないのに美しい。
タイトル通り、人生そのもののよう。なんでもない日々の暮らしに潜む驚きや感動を綴った作品。
『ステーション・イレブン』エミリー・セントジョン・マンデル(満園真木訳)

- 作者: エミリー・セントジョンマンデル,Emily St.John Mandel,満園真木
- 出版社/メーカー: 小学館
- 発売日: 2015/02/06
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (23件) を見る
2000年代初頭のSARS流行時はチャイナタウンから観光客が消え、ゴーストタウンのようになっていたトロント。
その出来事にインスパイアされたかのようなディストピア小説がこの『ステーション・イレブン』。国際都市トロントを舞台に、飛行機で彼の地に降り立った人々によって広まり、驚異的な感染力を誇るグルジア風邪が巻き起こす悲劇を描く。
SF的な描写よりも、巻き込まれていく人々それぞれの人生にフォーカスしているのが印象的。そして病気が蔓延していくのは、雪が降り積もる冬のことである。
韓国文学から1冊
『すべての、白いものたちの』ハン・ガン(斎藤真理子訳)
「白いものについて書こう」と決めた春。そのリストには、「ゆき」や「こおり」、「しろくわらう」が含まれている。そのうち季節は巡り、寒い寒い冬がやってくる。小さくて雪のように白い赤ちゃん、凍てついた街、まばゆく光る月。
散文詩のようなうつくしい文章に魅了され、次々とページをめくるうちにふと気がつく。ああ、生と死が語られているんだなと。
クリスマスが登場する2冊
『誕生日の子どもたち』トルーマン・カポーティ(村上春樹訳)

- 作者: トルーマンカポーティ,Truman Capote,村上春樹
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 2009/06/10
- メディア: 文庫
- 購入: 4人 クリック: 22回
- この商品を含むブログ (39件) を見る

- 作者: トルーマンカポーティ,山本容子,村上春樹
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 1990/11/25
- メディア: 単行本
- 購入: 7人 クリック: 36回
- この商品を含むブログ (27件) を見る
「クリスマスの思い出」は毎年クリスマスの時期が来ると読み返す物語。
鼻の奥がつーんとなるようなお話。
主人公は読者に「想像してみてほしい」と呼びかける。20年も前のクリスマスのこと。おばちゃんとぼく、犬のクウィーニーが一緒に過ごした最後の日々。ケーキを作り、ツリーを飾り、凧をプレゼントし合うだけなのに、2人と1匹のクリスマスは今でも思い出の中できらめく。
ニューヨークという都会に暮らし、時代の寵児となってもカポーティの心が帰って行く場所はいつだって南部の田舎町だったのだろう。そんなことを想像してしまう物語である。
『星のひとみ』サカリアス・トペリウス(万沢まき訳)
岩波世界児童文学全集に入っていて、大好きだったお話。これ絶版になっているのですね……悲しいな。今はもうこういう児童文学全集はないのだろうか。わたしは子どもに一体何を提供できるかしら。
こちらは、フィンランドの昔話を集めた作品。雪やオーロラがたくさん登場して、読んでいるだけで鼻の先がかじかんでくるような、ミトンが恋しくなるような。
クリスマスに拾ったサミ人の女の子「星のひとみ」の秘められた力や、指輪をはめておばあちゃんの少女時代を体験する女の子のお話など。
政治的な「冬の時代」を描いた2冊
『寒い国から帰ってきたスパイ』ジョン・ル・カレ(宇野利泰訳)
冷戦時のイギリス。イギリスの情報機関・秘密情報部で勤務するリーマス。
東側諸国と戦っているはずなのに、いつしか自身の仕事が民主主義的であるとは言えないと気づいてしまう……。個人と組織、仕事と恋愛、イギリスの諜報機関と共産主義。
それぞれの拮抗が彼を悩ませ続ける。少しくたびれたスパイ像は、『007』とは一味違ってリアル。
『ペルセポリス: イランの少女マルジ』マルジャン・サトラピ(園田恵子訳)
1979年にイランで起こったイスラム革命以降続いた、イランにとっての「冬の時代」を少女の視点から描くB・D(バンド・デシネ、フランスの漫画)。
ユーモアを失わない家族の愛に囲まれて育ったマルジは、イスラム革命後、自身や母、周りの人びとの自由が奪われていくことを感じる。そしてオーストリアに留学(脱出)することが決まるが……。
ちなみに続編では、ウィーンで寒い寒い冬を経験するマルジの姿も描かれている。
冬が舞台の8冊
『フローラ』エミリー・バー(三辺律子訳)
記憶障害を持つ少女フローラの大冒険を描いた物語。数時間前のことも覚えていられないフローラは、忘れてはいけないことをメモすることで毎日をやり過ごしている。
しかし、決して忘れない記憶が1つだけあった。それは大好きな男の子と浜辺でキスをしたこと。町を出てノルウェー領スヴァールバルへ旅立った彼を追って、フローラは生まれて初めて1人で飛行機に乗るのだが……。
恋愛もののYAと思いきやミステリーなどの要素もあって、途中でガラッと雰囲気が変わりページを繰る手が止まらなくなる。表紙の通り寒いスヴァールバルが舞台ということで、冬に読むのにぴったり。
『ゴーストドラム』(ゴーストシリーズ)スーザン・プライス(金原瑞人訳)
著者が北国出身のおじの話を思い出して書いたという作品。3部作。
金原瑞人さんの翻訳で本作だけ1991年に出版されていたのが、2017年のクラウドファンディング(サウザンブックス)で3部作すべて発売に! なんてラッキーなんでしょう。
物語を語るのは猫。舞台は雪が降り積もる北国。主人公は奴隷として生まれ、魔法使いの弟子になる女の子。眠り姫のように助けを待ち望む男の子、敵となる魔法使いのクズマ……。その展開の衝撃も、いつまでも心に残る。
最初の1冊のみならず、3部作すべて冬の読書にぴったり。そしてすぐに次の作品が読みたくなるので、3冊まとめての購入を強くおすすめします。
『キャロル』パトリシア・ハイスミス(柿沼瑛子訳)

- 作者: パトリシアハイスミス,Patricia Highsmith,柿沼瑛子
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2015/12/08
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (32件) を見る
冬の寒いニューヨークを舞台に、キャロルとテレーズという2人の女性の運命の恋を描く。デパートでの出会いのシーンがなんとも印象的でアメリカ東部的。
結末は予想外で、ある意味衝撃的。春の訪れを感じさせる。
『断絶』リン・マー(藤井光訳)
こちらも、冒頭の舞台はニューヨーク。ただし、文明が息絶えたあとのニューヨークだ。中国から全世界に広まったシェン熱が原因で、多くの人類が死んでしまう。しかし、ワクチンもないというのに、シェン熱患者と接触しても、なぜかシェン熱にかからない人々が一定数存在した。主人公のキャンディスもその1人で……。
ちなみにこれ、新型コロナウイルス感染症が流行する以前の物語。読んだときにはすごい〜ポストアポカリプス、ディストピアな世界!と思っていたのが、みるみるうちに世界がSeverance的な日常に突入していくのはsurrealで恐ろしかった。
『シャイニング』スティーヴン・キング(深町眞理子訳)

- 作者: スティーヴンキング,Stephen King,深町眞理子
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 2008/08/05
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 9回
- この商品を含むブログ (46件) を見る

- 作者: スティーヴンキング,Stephen King,深町眞理子
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 2008/08/05
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 6回
- この商品を含むブログ (37件) を見る
こちらは、ぬくぬくとお家で過ごす時に読みたい作品。スティーブン・キングのホラー作品は陰鬱な天気の日に、安全な場所で読んだらより楽しめるような気がする。
舞台はマイナス25度という極限の寒さ、積雪に閉ざされたコロラドの山の奥に位置するホテル。一冬の管理人として作家とその家族(妻と息子)がやってくるのだが、ホテルは悪名高き幽霊屋敷だった……。
『闇の左手』アーシュラ・K・ル・グィン(小尾芙佐訳)

- 作者: アーシュラ・K・ル・グィン,Ursula K. Le Guin,小尾芙佐
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 1978/09/01
- メディア: 文庫
- 購入: 12人 クリック: 388回
- この商品を含むブログ (103件) を見る
舞台は惑星〈冬〉、季節が巡っても氷が張り、ひねもす雪が降るような星だ。
国交を求めて使節として地球からやってきたゲンリー・アイは、この両性具有の人々が暮らす惑星で理解者を得ることができずジレンマを抱えていた。しかしとある事件がきっかけで宇宙人と心を通わせ、友情や愛を育むようになる。
ル=グウィンが真冬にソリを引く2人の人間(の写真? 映像?)を見たことがきっかけで生まれた作品だけあって、ゲンリーとエストラーベンの逃亡劇が心に残る。
Conversations with Friends / サリー・ルーニー
フィッツジェラルドの『夜はやさし』をモチーフにしたと思われるこの作品。『夜はやさし』は南仏の描写が美しく、登場人物たちが少しずつ壊れていく様が少し気だるく感じられ、夏に読むのにぴったりな1冊なのだが、こちらは逆に冬の読書にぴったりな作品。
夏を過ごすのもエターブル(フランス)で、どこか涼しい風が感じられる描写が特徴的。主人公がほとんどの時間を過ごすアイルランドのダブリンの冬は(実際は日本の冬とさほど変わらないのだが)読んでいるとこちらの手もかじかむ感覚に陥るほど。
10代、20代の方は、等身大の女の子の友人や恋人との会話を楽しんで。30代以降の方は青く若い日々に思いを馳せて。
Open Water / Caleb Azumah Nelson
「恋をするのは夏に限る、パーティーの後に一緒に歩いたり、屋外でゆっくりと時間を過ごしたりできるから」と思っていた「きみ」が美しい女性と出会い、恋に落ちたのは冬のできごとだった。引力が存在しているかのように引き寄せられ、どうしてもそばにいたいと強く思うのに、なんと彼女は友人の恋人で……。
若い2人の恋物語は、背景が冬だからこそ熱が感じられる。本作家のデビュー作。
「雨の日」リストもあります。




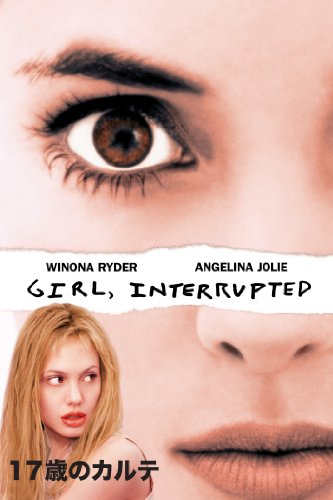






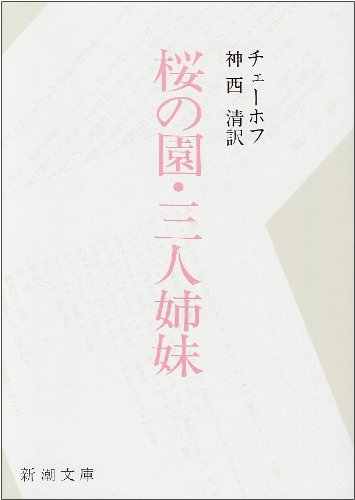









![魅せられて四月 [DVD] 魅せられて四月 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/216PKPZNAPL._SL500_.jpg)












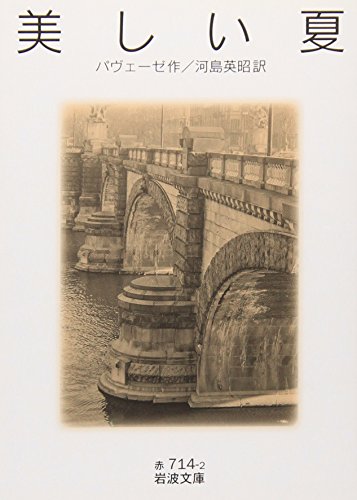

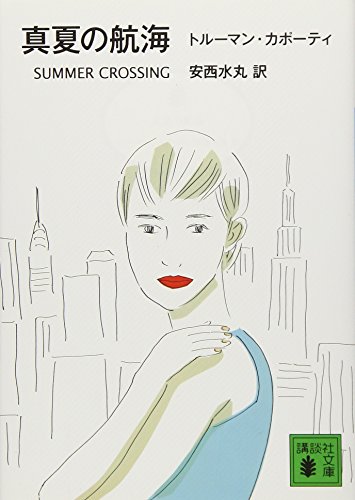




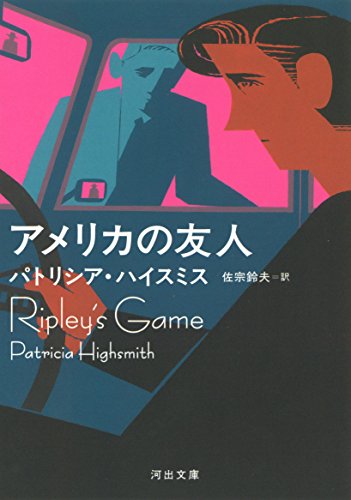

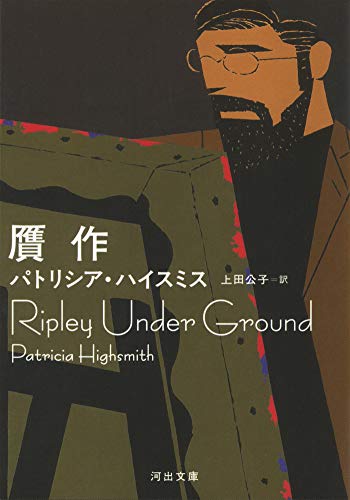

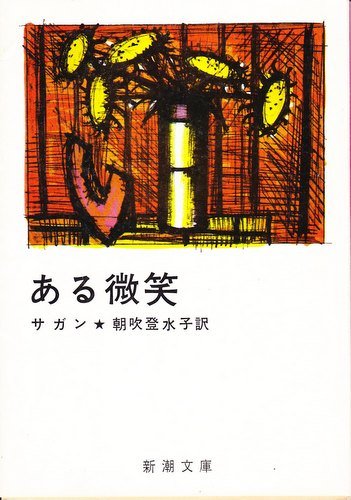




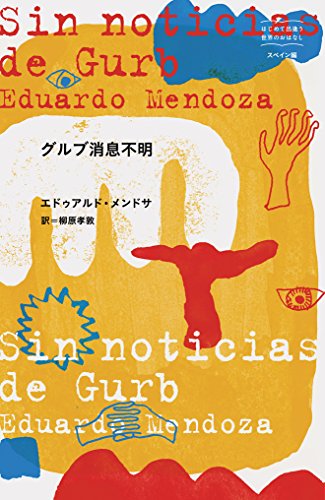



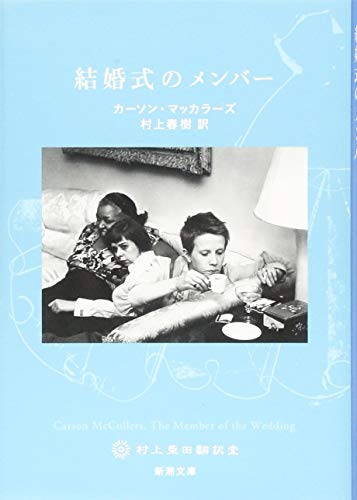


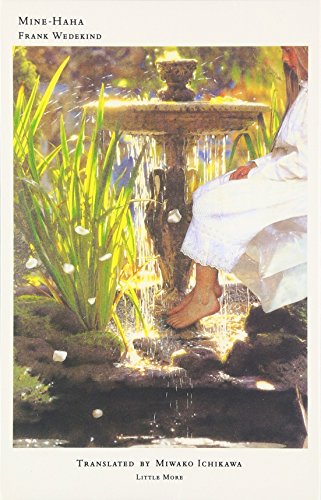
![エコール [DVD] エコール [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lopayAblL.jpg)
![ミネハハ 秘密の森の少女たち [DVD] ミネハハ 秘密の森の少女たち [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51joQV2k84L.jpg)