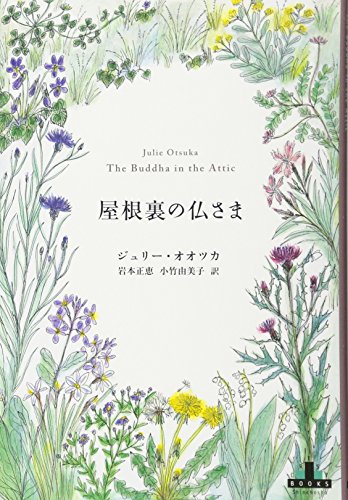[The Secrets We Kept]
なんて幸せなことでしょう。わたしが読んでいるこの本、わたし以外の人はもうみんな読んでいるなんて。世界文学好きも読んでいるし、ミステリ好きも読んでいるという相乗効果(?)で、普段共通の本の話題がない人とも、「あの本」を読んでいる人とも読んでいない人とも、盛り上がることのできた1冊。
「あの本」とは
ボリス・パステルナークの『ドクトル・ジバゴ』である。ロシア革命を批判しているととられたため、ソ連では出版を禁じられ、結局イタリアのフェルトリネッリ社からイタリア語の翻訳版が出版された小説だ。その後CIAのプロバガンダ政策に利用され、密かにソ連の人々の手にも渡った。
本作品によりパステルナークへのノーベル文学賞授与が決定したものの、ソ連政府が圧力をかけた。亡命したいとは到底考えていなかった(「母国を去ることは死に等しい」)パステルナークは、受賞を辞退せざるを得なくなる。
今も、そしてきっと当時も「どうしてこの本が?」と考えてしまうような愛の物語、それが『ドクトル・ジバゴ』(だとわたしは思う)。当ブログのレビューはこちら。執筆当時、宝塚歌劇団で『ジバゴ』が上演されていたためこんな題名ですが、記事の大半は小説について書いております(一応)。
ちなみに最高だった宝塚・星組公演はAmazon Primeでも視聴可能!
「東」と「西」の女性たち
この小説で描かれるのは、まさにパステルナークが生きるソ連(東)と、『ドクトル・ジバゴ』をソ連の人々の手に渡そうとCIAが暗躍するアメリカ合衆国(西)である。そして語り手は皆、女性たちだ。
東にはオリガがいる。パステルナークの長年の愛人であり、『ドクトル・ジバゴ』のヒロイン、ラーラのモデルとなった人物だ。オリガはパステルナークと関係したせいで強制収容所に収監され、想像を絶する過酷な生活を送ることになる。
西には、CIAでタイピストとして働く「わたしたち」がいる。その中でも、新しく部署に入ってきたロシア系の若い女性イリーナと、彼女をスパイとして教育することになる、OSS(戦略諜報局)の生き残りで経験豊富なサリーの2人に焦点が当たる。「わたしたち」は皆、表向きはタイピストだが、
それ以上のことをする者もいた。毎日、仕事を終えてタイプライターにカバーをかけたあとにした仕事については、ひと言も口外しなかった。男たちの一部とは異なり、わたしたちは秘密を守ることができたのだ。
『ドクトル・ジバゴ』は男性によって書かれた物語で、CIAのプロパガンダ作戦だって男性の手柄に焦点が当たりがちだ。
でも、わたしたちは考える。ジナイダやオリガが存在しなかったら、『ドクトル・ジバゴ』は書かれただろうか。日の目を見ることがあっただろうか。どんな場所であっても、そこには必ず女性がいて、さまざまな苦難を乗り越え、歴史を変え続けている。
実在のドロシー・ヴォーンはNASAで、映画『ドリーム』で描かれた以上に活躍していたことを、わたしたちは知っている。9,000年前の狩猟採集民社会では男が狩りをし、女は採集・子育てのみを行っていたというのは真っ赤な嘘で、女性のハンターが存在していたということを、2020年に生きるわたしたちは知っている。
女性たちは秘密を守るから(The Secrets We Kept)明らかになることはないかもしれない。それでも、わたしたちは知っている。そんなことに思いを馳せてしまう、女性たちの物語だった。
愛の物語
この小説のテーマは、と問いかけると返ってくる答えは読者によって違うはずだ。でもやっぱり、「愛の物語」なのだと思うのです。
登場人物たちは、何度も何度も自分や愛する人に問いかける。
なぜあなたは、愛だけじゃ足りないの?
なぜわたしは、愛されるだけではだめだったの?
まるで『ドクトル・ジバゴ』に登場するあの人やその人が問いかけたように。
パステルナークが何度も繰り返しソ連政府に語ったことは嘘でもなんでもなくて、彼は「愛の物語」を書き上げたのだとわたしも心から感じている。
「わたしたち」文学
この小説には「わたしたち」タイピストが語る章がある。
わたしが自分の人生について小説を書くとして、主語が「わたしたち」になるような期間はあったかなと、ふと考えてみた。もちろん、あった。「世界VSわたしたち」とまではいかなくても、どこかで自分はマイノリティだと感じたときが多いかもしれない。しかし、だからこそ数少ない「わかりあえる同士」との絆を深めた時期でもあったはずだ。
「わたしたち」が主語となる小説を集めてみた。
Las Manos Pequeñas / アンドレス・バルバ

Las manos pequeñas (COMPACTOS nº 735) (Spanish Edition)
- 作者:Barba, Andrés
- 発売日: 2019/09/18
- メディア: Kindle版
まず頭に浮かんだのが、『ミネハハ』のような女の子しかいない孤児院が舞台となったアンドレス・バルバの小説、Las Manos Pequeñas(小さな手)。
新入りの女の子マリーナを観察する視線が「わたしたち」として一体化することで、マリーナの抱えている孤独がより強く浮かび上がるようだった。
『悪童日記』アゴタ・クリストフ(堀茂樹訳)
「わたしたち」ではなく、双子の「ぼくら」だけれど、この物語は完全に「ぼくら 対 世界」という物の見方を描いている。 双子の育っていく様をどきどきしながら見守るが、同時にその心のなさにぎょっとして、汗が噴き出るようなこともある。ラストは圧巻。
『アフターダーク』村上春樹
それから、とても実験的な、村上春樹が「書く」手法を冒険しているような作品。内容としては、彼の長編小説の合間の息抜きという感じで、これを第1章として今にも長編が生まれ落ちそうな息遣いを感じる。まるで映画を見ているような視点で、「私たち」は物語を眺める。眠り続けるエリを観察する。マリと一緒に東京の夜を彷徨う。
『屋根裏の仏さま』ジュリー・オオツカ(岩本正恵・小竹由美子訳)
こちらでは、「写真花嫁」として渡米した日本人女性たちが結婚に失望し、厳しい環境で働き続け、子どもを生み育て、やがて戦争に巻き込まれる。「わたしたち」は同じ環境下に置かれる娘たちの相似性を表しているようでいて、その違いをも際立たせる。
『ボヴァリー夫人』フローベール(芳明康久訳)
そうそう、『ボヴァリー夫人』の冒頭も、「私たち」なのだった。夫が幼かった頃、転校してきた学校にいて、新入りの彼を目撃していた「私たち」。
読みたくなったブックリスト
『甘美なる作戦』イアン・マキューアン(村松潔訳)
同じような文学を通したプロパガンダ作戦を描いた物語がこちら。舞台はイギリスで、MI5に勤める女スパイが主人公。これも愛の物語だった。久しぶりに再読したいな。
『P.A. プライベートアクトレス』赤石路代
実はサリーの章を読みながら一番に思い出したのがこの漫画!
主人公の志緒は、個人に雇われて「自分ではない誰か」を演じる「プライベートアクトレス」。とびきり美しく、天才的な演技力を有しているのに表舞台に立たない理由は、彼女の出生にあった。
母親は国民的女優で、未婚のまま不倫相手との間に志緒をもうけたのだ。表舞台に立てないどころか、誰にも家族のことを話せないし、母親は忙しいので家政婦さんに育てられた志緒の孤独は深い。でも常に明るく振る舞い、秘密を厳守する姿勢はサリーに通じていると思う。
すごく面白い作品なのだけど、時代背景もあり(1990年代初頭)差別的な用語や視点が含まれている(具体的には「ホモ」)ことに注意。
Lara: The Untold Love Story and the Inspiration for Doctor Zhivago / アンナ・パステルナーク

Lara: The Untold Love Story and the Inspiration for Doctor Zhivago
- 作者:Pasternak, Anna
- 発売日: 2017/01/24
- メディア: ハードカバー
『ドクトル・ジバゴ』の記事でも読みたいと書いた、ポステルナークの姪によるオリガについてのノンフィクション。
『パステルナーク 詩人の愛』オリガ・イヴィンスカヤ
こちらはオリガによる作品。彼女は何を考え、何を見ていたのか知りたい。図書館に行ったらあるかなあ。
『ローズ・アンダーファイア』、『コードネーム・ヴェリティ』エリザベス・ウェイン(吉澤康子訳)
本作を訳された吉澤さんが訳者あとがきで、「この2冊を持ち込みで訳したことがきっかけで、本書の翻訳を打診された」と書かれていて、そんな編集者さんも翻訳者さんもつながりを感じる小説、面白いに違いない! 読みたい! となった。
ミステリは本当に全然読んだことがなく(アガサ・クリスティーくらい)知らない作品ばかり。でも、これからたくさんの優れたミステリ小説に出会うことができるのだと考えると、これまたなんて幸せなのかしら。人生の楽しみは続く。
わたしの友人「ラーラ」の愛の物語
もう『ドクトル・ジバゴ』に関する小説ということは知っていたので、いざ買い求めてびっくりしたのは著者の名前。なんと「ラーラ」・プレスコット。『ドクトル・ジバゴ』のヒロインと同じ名前ではないですか。訳者あとがきによると、『ドクトル・ジバゴ』好きの両親によって付けられた名前だとか。
(ここからは小説とまったく関係のない思い出話です)
わたしの人生にも、「ラーラ(Lara)」が存在する。大学時代のたった1年を一緒に過ごしただけなのに、今もなぜか仲のいい友人だ。このラーラも相当な愛の物語を生きているのが、偶然というかなんというか、不思議だなあと読みながら考えていた。
ラーラとは、大学1年生のときの寮の部屋が隣で、フランス語の授業でも一緒だったことがきっかけで仲良くなった。「箸が転げてもおかしい年頃」とはよく言ったもので、この1年は本当に笑ってばかりいた気がする。周りもみんな新しい環境で、新しい恋愛が始まったりして、なんとなく浮かれていた。でもラーラは違った。大学入学の半年ほど前に、運命の出会いを経験していたのである。
相手はロシア人男性。ラーラもロシア系で、ロシア語は母国語ではないにしても堪能だし、さぞかし楽しいお付き合いだろうと思いきや、まったくそんなことはなかった。ラーラの家族がアルメニア系なのに対し、彼はアゼルバイジャンにルーツを持つロシア人だったのだ。
2020年の現在でさえナゴルノ・カラバフ紛争が勃発しているアルメニアとアゼルバイジャン。ラーラの家族は激怒し、交際に反対した。その上仕事で北米に滞在していた彼もロシアに帰国することとなり、2人は先が見えない遠距離恋愛に突入していた。大学入学当時は「彼がSkypeでこんなことを言ってね、あんな表情をしてね」とそれはそれは楽しそうに話していたラーラも、次第に沈んだ顔を見せるようになっていた。
自分の家族も彼の家族も、別れろとしか言わないとこぼすようになった。真冬に一緒にバスを待っているとき、彼の話をしていたラーラがぼろぼろと泣き出したことがあった。マイナス20度にもなる極寒の地である。涙は目からこぼれ落ちるが早いかパッキパキに凍り、ラーラの顔に張り付いた。あれはちょっと面白かった……2人で大爆笑したのを覚えている。
でも、春がくる頃には、「もう駆け落ちするしかない。大学を辞めて彼のところに行きたい」なんて言うようになっていた。表向きは心配していたわたしだったが、内心は「おいおいおい……大丈夫? 今大学辞めてロシアに行って一体何するの?」と思っていた。『アリとキリギリス』で例えるなら100%キリギリスな上、すぐ目の前のことしか考えられないわたしにとって遠距離恋愛なんて机上の空論、周りを見渡してみればきっともっといい人いるよ? と本人にはとても言わなかったものの、彼女の気持ちを想像することすらできなかったのは事実だ。
ラーラは結局、1年生が終わる夏に、大学を自主退学しロシアに渡った。両親にはもちろん大反対され、絶縁するような形だった。海の向こうの人になっちゃったラーラとわたしはそれでも頻繁にMSN Messengerで(時代)やりとりして、近況を話し合った。
ラーラは先へ先へと進み続けた。ロシアで大学を卒業し、仕事を始め、彼の仕事の都合でフランスに移住するとフランス語を再習得し、今はなんと通訳者として勤務している。最近はSNSの投稿も全部フランス語になっちゃって。その間に子どもも3人生み、今や全員小学生に。孫を目にした双方の両親との冷戦はたちまち終焉を迎えたという。
すごく大変なことだって多かったろうに、ラーラは決して弱音を吐かなかった。いつも「元気だよ」、「楽しくやってるよ」と笑顔で話してくれた。それは今も変わらない。きっと少しでも愚痴を言ったら、「それ見たことか」と言われると思っているのではないかな。誰にも愚痴は言えないのかもしれないと考えるときもある。
ラーラにとっては、愛がすべてだった。あまりに盲目的に突っ走る姿には「絶っっ対後悔する! やめときなはれ!」と何度も言いたくなったけれど、今なお仲睦まじい夫婦の写真を見ていると、その決断は最良の選択だったのだと改めて思う。
どうしてラーラは、たった18歳やそこらで、これが「愛」だとわかったんだろう。人生をかける価値があると、どうしてわかったんだろう。いや、反対かな。それほど「愛」を大切にできる2人だったからこそ、そして愛し愛されていたからこそ、ここまでやってこれたのかもしれない。
日本語で読むことがないのをいいことに、色々書いちゃった……ごめんねラーラシカ。当時は『ドクトル・ジバゴ』を読んだことがなかったから、「ラーラってドクトル・ジバゴからきてるの?」なんて聞いたことがなかったなあ。今度聞いてみよう。